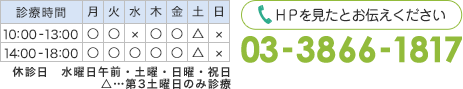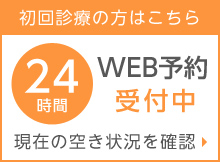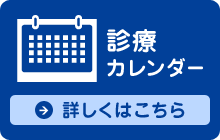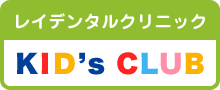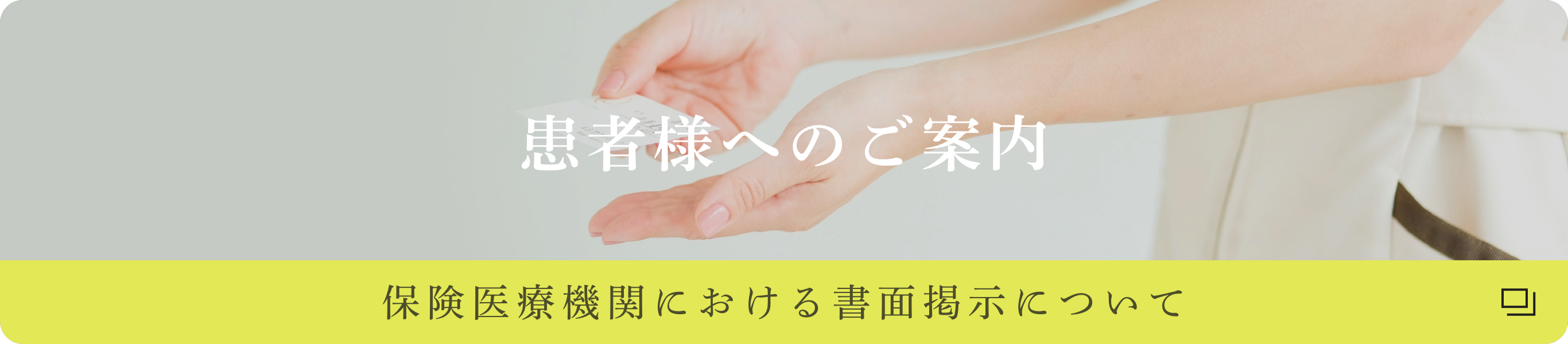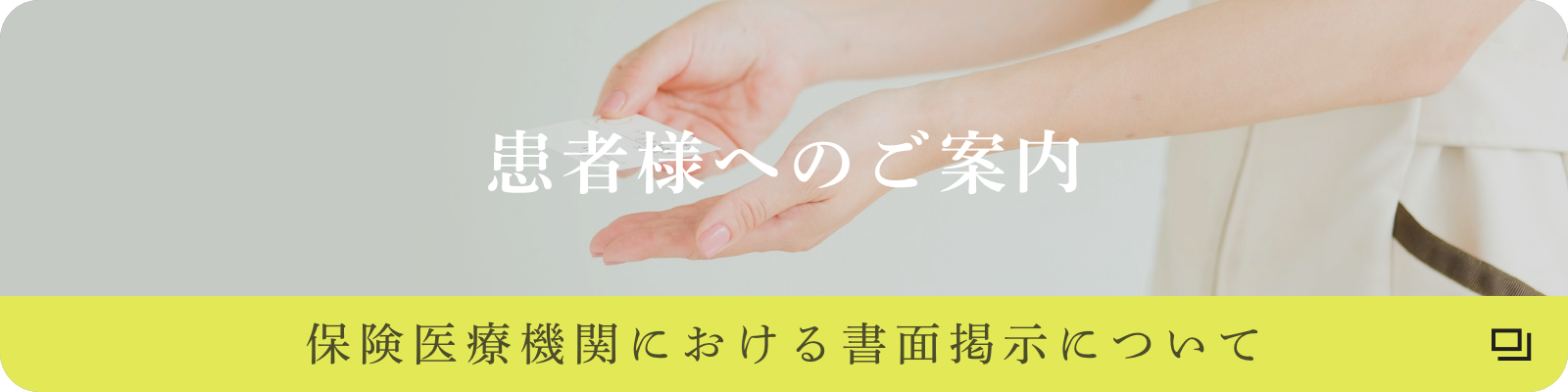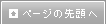あすなの日常
-
2018年4月 24日 火曜日
ハーバード大学歯学部研修
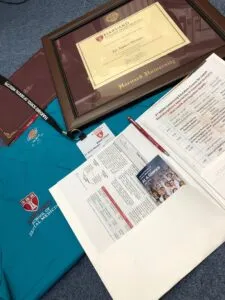
こんにちは。レイ歯科の新保です。
2月から、また噛み合わせのセミナーのオブザーバー参加が始まりました。
今回は、きちんと消化出来るよう拝聴したいと思います。
また、2月には、患者様やスタッフ、家族の協力があり、ハーバード大学での歯学部の研修会に参加させて頂きました。
様々なジャンルの講義を受け、勉強熱心な先生方と知り合えて大変刺激になりました。
アメリカの保険制度は、日本とはかなり違い、歯科は含まれていないことが多く、高額な治療となります。
お金をかけられる方は、最先端で高度な治療を受けられ、かけられない方は、最低限の治療しか受けられない現実があります。
低所得者の為のヘルスケアセンターも見学させて頂き、とても勉強になりました。
改めて、日本の保険制度は本当に手厚いと思いました。
17年間ハーバードで教鞭をとり、今回のセミナーでもプランニングや受講生の為にご尽力して下さった女医先生と出会う事が出来、とても素敵で憧れてしまいました。
また、先日5月に憧れの女医先生と再会できる会のお知らせを頂き、今から楽しみにしています。
日々学んだ事をレイ歯科・矯正歯科の患者様に還元できるよう研鑽をつんでいきたいと思います。 -
2018年4月 10日 火曜日
口腔機能のお話
桜の花もすっかり新芽に変わり日ごとに温かくなってきましたね。
まだ、気温差が激しいので体調を崩さないよう気をつけて下さい。
本日は、口腔機能についてお話したいと思います。
口腔機能とは、離乳食時期から噛む学習と訓練により習得されます。
この学習により、噛み合わせや唇の自然な姿になり、未熟な習得では、終生にわたり
不自然な形になってしまいます。
不自然なお口のチェック項目
1. 唇 2.舌 3.上顎の内側 4.乳歯列 5.横の歯の萌出位置
6.顔面 7.姿勢 8.呼吸 9.習癖 10.発音 などです。
口唇のチェック項目
1.上唇が山形になっていないか? 2.唇の硬さ軟さは、どうか?
2.口角は、下がっていないか? 4.唇の粘膜部が見えていないか?
5.あごに緊張は、ないか?
完成期までに、噛み方が悪く唇、舌の使い方、噛み合わせの調和がとれて
いないと、お口ポカンだったりぺちゃぺちゃ食べになってしまいます。
以上の点に注意し1つでも該当があれば早めに歯科に相談して下さい。
早期に治療し健やかな口腔機能へ導きましょう。 -
2018年3月 6日 火曜日
噛み癖のお話
日ごとに温かくなり、毎日春の訪れを楽しめる季節になってきましたね。
本日は、噛み癖についてお話させて頂きます。
噛み癖とは・・・一部の歯ばかりで噛む癖を噛み癖と言います。
例えば、前歯ばかりや片方の奥歯ばかりで噛んだりする事です。
乳歯は、前歯から生えてくるのでついつい前歯ばかりを使いがちになってしまいます。
奥歯期になったら、注意深く観察し奥歯を使い左右で噛む習慣をつけていきましょう。
テレビを見ながらの食事は、片側噛みになりやすいですので注意してあげて下さい。
決まった歯ばかりで噛んでいると顔が非対称になったり、口元のバランスが悪く
なったり、姿勢にも影響を及ぼします。
噛みあわせが悪くなると、頭痛や肩こりなど体調にも影響がありますので、噛みだしのこの時期から親御さんで注意深く観察願います。 -
2018年2月 10日 土曜日
習癖と態癖のお話
本日は、お子さんの習癖と態癖についてお話させて頂きます。
習癖とは・・・ 習癖とは、指しゃぶり、爪噛み、ハンカチ(タオルなど)しゃぶりなど口の中に絶えず何か入れる習慣の事で、口唇や歯並びに影響を及ぼします。
上記のような癖を続けていると、上口唇が上向きになりお口ポカンになりやすく噛みあわせも開口になりやすいです。
乳児の指しゃぶりは、自然の姿です。無理にやめさせなくてもよいですが、3歳すぎて習慣が治らなければ、お外で遊んだり、手を使う遊びなどして気をそらして治してゆきましょう。
なかなか治らなくても強く叱ったりせず、やさしく導いてあげて下さい。 おしゃぶりも長年使用擦ると開口になりやすいので注意して下さい。態癖とは・・・
態癖とは、うつぶせ寝や横向き寝、頬杖などの癖です。いずれも、外側から下顎を強い力で押してしまい噛みあわせが偏位する事があります。
顎関節を強く圧迫すると顎関節症などになりやすくなりますので気をつけて下さい。例年以上にインフルエンザが猛威をふるっているようです。くれぐれも皆様のお体ご自愛くださいませ。
-
2018年1月 16日 火曜日
完成期(3歳以降)パートⅣ
早いもので1月も半ばになってしまいましたね。今年も宜しくお願い申し上げます。
新年最初のお話は、3歳頃の完成期について書かせて頂きます。
「完成期」とは、乳歯が生えそろった段階を完成期と言います。
この時期は咀嚼と同時に飲み込みも上手になります。良い飲み込み方とは、食べ物をゴックンとした時に喉の筋肉がわずかに動く飲み込み方です。飲み込む時に口や顎の筋肉が緊張してしまうのは、正しく飲み込めていない例ですので注意深く観察してあげて下さい。
初めて食べ物を口にした時から少しずつ段階的に正しい噛み方、咀嚼の仕方、舌の動きや顎の動きなどを覚えていき正しく出来るようになると自然な口元になってきます。将来の「食べ方の基礎作り」のこの時期を大切にお子様と練習して頂きたいと思います。
この時期の注意点
・口を閉じてリズミカルに咀嚼出来ていますか?
・片側ばかりで噛まず両側の奥歯をきちんと使っていますか?
・口を開けたまま「ペチャペチャ」「クチャクチャ」と音を立てていませんか?
・食品をよく噛まずに大きなまま「ゴックン」していませんか?上記に注意することによって、正しい噛みあわせが出来、歯並びが良くなり虫歯や歯周病などにかかりにくくなります。
ご家庭で実践して疑問や分からないことがありましたらいつでもご相談下さい。 -
2017年12月 27日 水曜日
奥歯期(1歳殻~2歳頃)パートⅢ
本日は、「奥歯期」についてお話させて頂きます。
前歯期からしばらくすると、奥歯が萌出します。奥歯を使って噛めるようになる時期を「奥歯期」と言います。
奥歯が萌出し、咀嚼が出来るようになると歯根膜を通じて食べ物の硬さや柔らかさ、大きい、小さいと言うことが認識出来るようになります。
この時期は、噛む力や咀嚼のリズムを身に着けることがとても大事な時期になりますのでお子様が、食べ物を口に入れたらゆっくりと噛んで咀嚼する時間を与えて下さい。
お子様にとっては、リズムを掴むのに多少の時間が必要になります。 お子様の脳と口で情報の伝達が行われ、噛む力の強弱、咀嚼のリズムなど舌の使い方などの訓練になる時間です。この時期は、口の中にたくさんの食べ物を押し込まず十分に噛み、咀嚼できるように練習することで脳にも良い記憶としてインプットされ、その後の歯の育成にも良い影響を与えることが出来るようになります。 食べ方の注意は、口唇を閉じて噛むこと。口に入れた食べ物が見えないような食べ方をしているか、早食いや口の中に食べ物が残っているのに飲み物などで流して飲み込んでいないかに注意して見てあげて下さい。
以上の点に注意しお子さんの食べ方に注意深く気を配って頂きますと3歳になる頃には、正しい噛み方、咀嚼し飲み込む方法の基本が学べることでしょう。 お子様の歯の育成についてご相談、ご質問などありましたらいつでもご連絡お待ちしております。 本年は、大変お世話になりありがとうございました。次回は来年早々の更新とさせて頂きたいと思います。
引き続きご愛読お願いいたします。 来年度も皆様の健やかな歯の健康に尽力させて頂けますよう願っております。レイ歯科矯正歯科 新保 礼子
-
2017年11月 14日 火曜日
前歯期(1歳~1歳半頃)パートⅡ
今回は、1歳から1歳半ごろの前歯期についてお話したいと思います。
「前歯期」とは?
上顎4本、下顎4本の前歯が萌出して前歯が使えるようになる時期を「前歯期」といいます。
「前歯期」の特徴
・食べ物を、自らの手でつかんで口に運び、前歯で噛み切る事が出来るようになります。
噛み切ることの経験を重ねることで、「一口の量」の感覚を身に着けていきます。
ここでも、「食べ物の運び方」が重要になり食べ物を口の奥まで入れすぎないよう、注意深く見守ってあげて下さい。
食べ物を奥まで入れてしまうと、口唇と前歯を使い食べ物をとらえる感覚が身に付きません。
この時期に記憶した「一口の量」は、脳に記憶され生涯の自分の「一口の量」としての基礎となり次への成長へ続いていきます。
・コミュニケーション能力や意欲、思考をつかさどる前頭前野が急速に発達します。
お食事は、ご家族で声を掛け合いコミュニケーションを取りながら食事をする。
食べ物のの色や形、それぞれの香りも感じられるよう工夫する。
味付けは、食材の味を引き立たせるため薄味にする。
・舌は、前後、上下に動きます。(奥歯期へ移行する時期は、下顎が左右に動いてきます)「前歯期」の注意点
口唇と前歯を適切に使い、口唇の周囲筋の口輪筋の発達を促し鼻呼吸の習慣を身に着けましょう。
しっかりと口を閉じ前歯が使えているか注意して下さい。このように「前歯期」は、幼児が人として生きる第一歩「前頭前野」が発達する大事な時期です。
楽しく色鮮やかな食卓を囲み、五感を使い味覚を鍛え、口唇と前歯を使い噛み切る動作を身に着け
「一口の量」を覚えていきましょう。 -
2017年10月 24日 火曜日
乳歯の萌出のお話Ⅰ
今回は、乳児から幼児期へのお口の発育、発達についてお話したいと思います。
第一弾として乳歯の萌出についてのお話を書かせて頂きます。歯が生えてくる前の無歯期は、噛むことは出来ず舌の運動も不十分で舌を前後に動かす事しか出来ません。
この時期に注意して頂きたい事が、唇をしっかりと使い捕食をする事です。
ポイント
・お子様自身が上の唇をキュッと閉じて食べ物を捉える
・食べ物を完全に口の中まで入れてしまわない
唇をしっかり閉じて、スプーンの上の離乳食を自分の口で捉えて中に入れる動作を繰り返し行います。ハイハイの重要性
ハイハイは、頭をぐっと上げた姿勢をキープして動き回る為、首回りの筋肉、肩の筋肉が自ずと鍛えられ食べる為には欠かせない筋肉の発達につながります。
二足歩行に至るこの時期にこそ充分にハイハイさせ、首や肩の筋肉を鍛え咀嚼に重要な筋肉をつけましょう。離乳食
離乳食は、お子様の発達に合わせ舌を前後に動かし食べられる柔らかなものから始め唇を使っているか確認しながら与えましょう。ゴックン時期から徐々に舌でつぶせる硬さに進めて行きましょう。
唇を鍛えていくことが正しく「噛む」ことにより、お口ポカンの防止にもつながります。
注意する事
食べ物のスプーンを赤ちゃんの唇に優しく当て、赤ちゃん自ら唇を下げて食べ物を捉えさせる。
唇が下がる前に慌てて口の奥までスプーンを運ばない。日々の習慣がお子様のお口周りの発育、発達をより良く成長を手助けしてくれます。
あまり気張らず試してくださるとよいかと思います。 -
2017年10月 17日 火曜日
研修会
院長のしんぽです。
九月に静岡の先生の研修会に参加してまいりました。
たくさんのお子さんを治療され、はならびだけでなく、バランスよく成長するようにAustraliaで開発されたMyobracのトレーニングを効果的におこなっていらっしゃる先生の研修会でした。レイ歯科でもMyobraceによる矯正の患者様たちもかなり成果がでております。
Myobraceの成果をよりえるためには、鼻呼吸がキーポイントです。
やはりお口ぽかんは、弊害をもたらします。
今回は、お口ぽかんの弊害についてお伝えしたいと思います。お口ぽかんの弊害
①口呼吸になりやすい
②かみ合わせが不安定になる
③前歯がでっ歯になりやすい
④上あごがV字になりやすい
⑤くちもとが不自然になりやすい
⑥はつおんが悪くなるお子様がいつもお口ぽかんされていましたら、優しく注意してあげてください。
-
2017年5月 20日 土曜日
5月第三土曜日診療日
院長のしんぽです。
今日は、第三土曜日で診療日です。
先週には、神田祭が。今週は、三社祭り。来週は、氏神さまの銀杏岡八幡さま。そのあとは、鳥越まつりと
近隣でのお祭りシーズン突入です。来週の土曜日は矯正出張日で、日曜日にはセミナーのため、岡八幡さまのお祭りは見られなくて残念です。
今日は、来週のセミナーに向け勉強しなくてはいけないのですが、スタッフや治療に来てくださっている友人親子と
三社祭り気分を楽しみに浅草に行こうかと…来週の咬み合わせのセミナーに向け三社祭り後は、月曜日から勉強ウィークです。