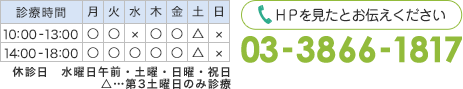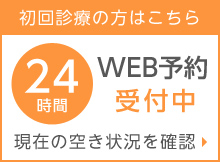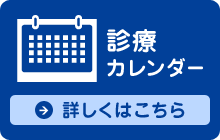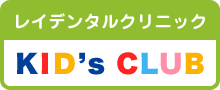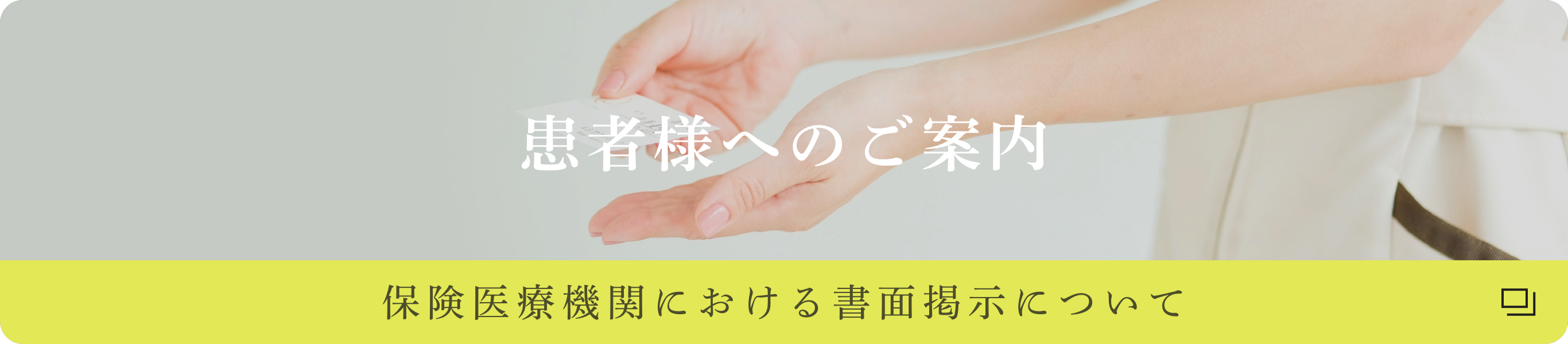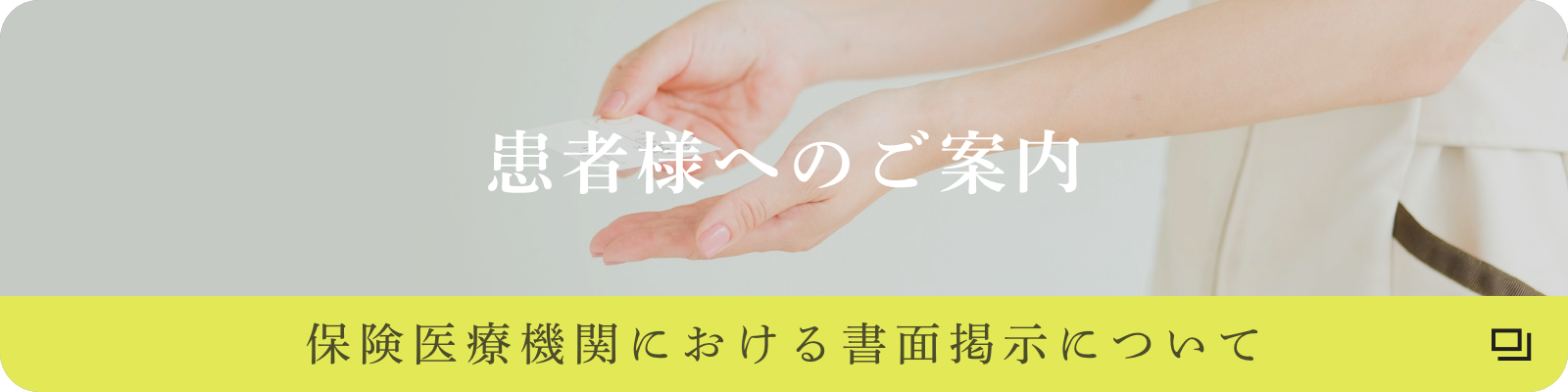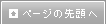病院からのお知らせ
- あごの小さい子が急増中!!
最近「あごの小さい子が増えた」と、歯科関係者達の共通の意見です。
あごが育たないと歯並びが悪くなるだけではなく、しっかり噛む事ができなくなり、
体内での消化吸収がうまくいかず体の成長や健康にも影響がでてきてしまいます。何故顎が育たなくなってしまったのでしょうか???
それは「噛む回数が減り、顎の運動量が減った」からです。
全身の筋肉や骨は、運動する事で育つのと同じように顎も噛むことで成長します。
しかし現代の子の噛む回数は戦前の半分以下、弥生時代と比較すると、なんと6分の1以下と、激減しているそうです。
噛む回数が減った理由として、噛まずして飲みこめる洋食よりのメニューが好まれるようになってきたからではないかと推測されます。では、回数を増やすためにはどうしたら良いのでしょうか?
噛み応えのある食事というと「硬いもの」を思いがちですが、そうではありません。
「何度もかむ必要のある食品」ということです。
たとえば根菜類であるゴボウ・レンコン・にんじん・大根・さつまいもなどを少し大きめに切ったり、高野豆腐・ひじき・わかめ・生野菜を毎食取り入れるだけでかむ回数が増やせます。
日々の食を少し見直すだけで噛む回数が飛躍的に増えていくので是非食卓に取り入れてみてください。レイ歯科では虫歯予防の話と共に食育の話しもしながら子供達の成長のお手伝いをさせて頂いています。
- ただで出来る口臭予防!
皆様お久しぶりです。
今回は「口臭について」お話していきたいと思います。さて、日常生活で自分の口が臭いかも?!と、思った経験がある人も多いのではないでしょうか。
「口臭白書2019」によれば、国民の90%は口臭を気にしているという結果がでています。
口臭には健康な人の起こす生理的口臭(起床時、空腹時、緊張時、ストレス時等)と、病気から起こる病的口臭(糖尿病、肝疾患、腎疾患等)があります。
このことから病気でなくても口臭は日常的に発生することがわかります。病的口臭に関しては各専門の病院で治療を受けて頂き、生理的口臭に関しては日常生活の中で少し意識してもらう事で口臭の改善へとつながります。
では日常生活で何を意識したら良いのでしょうか??
歯磨きや舌ブラシで口腔内を清潔にしておく!!もちろんこれは大前提ですが、実は一番重要な事が「唾液の分泌量と流れ=舌を沢山動かす事」です。
唾液の分泌が減る緊張時、ストレス時、空腹時、口腔内が乾燥してきたと感じられた時には、口を閉じた状態で口腔内で舌を動かす事により唾液がジワジワ湧き出るのを感じられるはずです。流れの早い淀みない川のように、皆様のお口も新鮮な唾液が絶え間なく流れいつもクリアなお口の環境を保っていただき口臭軽減に繋がる事を願い今回の投稿を終わりにしたいと思います。
- 糖質との上手な付き合い方
こんにちは。桜の季節もあっという間に過ぎ、植物は早々に初夏の準備に入っているようです。若葉の美しい時期、卒業や入学で新しい生活を始める方も多いと思います。いろいろと不自由の多い社会ですが、すべての方が希望に満ちた未来へ前進できるよう願っております。
今日は、前回に続きアンチエイジングの栄養学についてお話したいと思います。前回は、鉄とビタミンCでしたが今日は糖質との上手な付き合い方に触れていきたいと思います。昔から「砂糖は、虫歯の元」や甘いものに対する口腔環境への悪者というイメージが強い糖分ですが、歯だけではなく、健康を維持し健康寿命を延ばす為には「糖分(糖質)とどううまく付き合っていくか?」という課題にいかに知識を持ち、実際の生活に活かせてゆけるか?・・という事に繋がります。
今や、国民の10人1人は糖尿病及び糖尿病予備軍と言われる時代になりましたが糖尿病の進行に伴って生じる合併症は、健康寿命を縮める大きな因子となります。
一般的に健康な方の血糖値は、食後のピーク時でも140mgを超えることはありませんが140mgを超えた数値が下降せず長く続く状態を「食後高血糖」といいます。
「食後高血糖」が「慢性炎症」を引き起こし神経障害や血管障害の合併症だけでなく、がんや認知症などにも影響を及ぼします。
「食後高血糖」によっておこる糖とタンパク質が結合する反応である「糖化」も病気や老化を防ぐという意味では、見過ごすことはできません。
「糖化」したタンパク質は、段階を追って最終糖化産物(AGEs)となります。ここまできてしまうともはや元の物質に戻ることは出来ません。
また、血管や神経、気管支などの細胞にはAGEsと結合する受容体(RAGE)が存在し
その2つが結合してしまうと細胞の正常な働きを妨げます。
歯周病について、糖尿病患者の歯肉にはAGEsが蓄積していること歯周病を持つ糖尿病患者のRAGEが健常者よりも増加していることなどが明らかになっています。
次回は血糖値制御の重要性について触れていきたいと思います。
- ビタミンCと鉄について
こんにちは!
少し間が空いてしまいましたがすっかり寒くなりいよいよ冬本番になってしまいましたね。皆さん、くれぐれもお身体に気を付けて下さい。
今日は、前回からの続きでビタミンCと鉄についてお話させて頂きます。
ビタミンCは、疲労回復や美肌効果、鉄は、貧血の改善などの効能は一般的に広く知られている事と思いますが、歯科臨床上でもとても重要な役割を相互に関係しながら担っています。
ヒトやサル、モルモットなどは、たった1つの酵素を欠いているだけで体内でビタミンCを生成することが出来ません。健康を保つ上でとても大事な栄養素ですが食事やサプリメントで口から栄養を補充しないと欠乏症が起こり、あらゆる問題が身体に起こってしまいます。ビタミンCの役割として、ステロイドホルモンの合成、脂質の消化吸収、効率的なエネルギー確保などがあります。
ビタミンCは、腸管から吸収されますが、摂取量が多くなるに従って吸収率は下がってしまいます。サプリメントなどで摂取する時は、1度にたくさんではなく、少しづつこまめに摂取していく方が効果的でしょう。
ビタミンCと鉄は、体内で活性酸素を除き不要なものや有害なものを体内から取り除く働きもあります。
歯科でも近ごろは、ずいぶんと少なくなってきましたが、メタル治療を行う歯科医療においても不要なものを体外へ排出する作用は、重要な機能の1つとなります。鉄には、タンパクと結合している有機鉄(ヘム鉄)と結合していない無機鉄があります。
動物性食品に含まれる鉄やヘム鉄サプリメントには、有機鉄が含まれ植物性食品や医療品の鉄剤の多くは無機鉄です。
鉄が吸収されるには、二価のイオンである必要があり有機鉄は、そのまま吸収されますが、三価である無機鉄は、還元作用を受ける必要がありビタミンCとともに鉄を摂取すると二価に還元され吸収されやすくなります。
鉄が有効的に体内で運搬されるためには、亜鉛、ビタミンB6などが必要で総合的な栄養状態の改善が必要になります。
- タンパク質と歯の関係
こんにちは。暑かった夏も終わり台風や紅葉の季節になりますね。
朝晩の気温の変化も激しいので皆様体調にはくれぐれもお気を付け下さい。
前回、「アンチエイジング」のお話をしましたが、今日はより具体的にどのように歯の健康を保って心身共に若々しくいられるか?
と言うところに触れていきたいと思います。
まず、既に皆さんご存知かと思いますが、日々のバランスの取れた食事。栄養素が身体に与える影響からお話したいと思います。
私たちが普段口にしている食物に含まれる栄養素のうち、タンパク質・脂質・炭水化物は「3大栄養素」と呼ばれ最も基本で大事な
栄養素とみなされています。
この3つの栄養素は、「生命活動を維持擦る為のエネルギー源」なのです。中でも、タンパク質は生体内でより多彩な役割をはたしており、エネルギー源以外でも重要な側面を持っています。
たんぱく質は、皮膚・粘膜・爪・毛髪・消化管上皮・筋肉などの基本的な構成成分です。
軟組織はもちろん、硬組織の気質(骨組み)として重要なコラーゲンもタンパク質です。
タンパク質の代謝がスムーズに行われることは、歯肉、歯槽骨などの歯周組織の健康維持に非常に重要です。
・歯周組織のコラーゲン交代率
歯周組織のコラーゲン代謝は、歯槽骨で6日。歯肉で5日と非常に活発ですが、中でも歯根膜は、わずか1日と非常に短いことがわかっています。
歯周組織は、創傷の治癒能力が非常に高い反面、栄養不足による影響をきわめて受けやすい組織と考えられています。
・歯肉とコラーゲン
ヒト歯肉のうち約6割は線維性タンパク質で、おもにコラーゲンで出来ておりビタミンC
の欠乏によりコラーゲンの合成が阻害されると歯肉出血の原因になります。
・歯根膜のコラーゲン
歯根膜の線維成分のほとんどはコラーゲンで、前途したとおり非常に代謝が活発です。
その為に歯列矯正や象牙移植手術が可能になります。
・歯槽骨のコラーゲン
無機質成分を除いた骨の有機質成分は全体の1/3でその8割以上がコラーゲンです。
コラーゲンは、骨の基本的な気質として非常に重要で骨質に大きく影響すると言われています。外科的措置の多い歯科では、スムーズな創傷の治癒を促すことは重要なテーマです。
コラーゲンの基本的な骨組みは、3本のコラーゲンタンパクが紐状に絡み合った「3重らせん」ですが、その形を作るために必要な栄養は、ビタミンCと鉄です。
次回は、ビタミンCと鉄についてお話させて頂きます。
- 「元気」で「長寿」へのアンチエイジング
こんにちは。
今日は、人生100年時代突入において、より長く「元気」に「長寿」できるよう歯のアンチエイジングについてお話させて頂きます。
近年、口腔の機能を良好に保つことが生活習慣・食習慣と相まって全身の健康維持に深く関わっているという研究成果が世界的にあきらかになりました。とくに、体に異常が現れる前の「未病」状態で歯科が関与することで、病気の発症を未然に防げる見込みが大きいのです。健康体のドミノ倒しの最前列は、歯科医療です。
奥に行けば行くほど重い病気「脳卒中」や「心筋梗塞」など命に係わる重大疾病になります。
最前列の、歯科医療の前には「食生活」や「生活習慣」があり、今から乱れを見直し歯の健康に努めて下さい。アンチエイジングに遅すぎるという事はありません。
気づいた時から見直し、実践することによりどなたでも、「元気」な「長寿」社会への一歩につながるのです。
次回からより詳しく実践方法へと解説したいと思いますので、よろしくお願い致します。
- 新型コロナウィルス感染症予防対策について
こんにちは。久しぶりのスタッフブログ投稿です。
世間では、新型コロナウィルスによる自粛活動が広がっておりますが今日は、歯科医療における立場から感染症への対策についてお話したいと思います。口腔内の衛生状態が悪化することにより、口腔細菌が増加するとウィルスの感染力が増し
ウィルス性肺炎や人工呼吸器関連肺炎を憎悪させてしまいます。
特に、高齢者や基礎疾患がある場合日頃から口腔細菌数を一定にコントロールする必要があります。
コロナウィルス感染のレセプターは、舌の粘膜に豊富にあり経口感染には特に注意が必要です。各自の舌ブラシや殺菌剤などが入った口腔洗浄剤などによるケアとともに定期的な歯科医院での口腔内健診により口腔細菌由来の肺炎を防止し、新型コロナウィルス感染時の重症化予防に務めましょう。歯周病予防も同時に治療が必要です。
他に、咀嚼機能が低い状態が長期間続くと栄養摂取の偏りにより血中アルブミン値が低下してしまい、著しい免疫力低下を招いてしまう事になります。また、糖尿病悪化のリスクにもつながってしまいます。急性感染症と口腔衛生と栄養摂取は、感染予防及び重症化阻止に深く関係しますので日ごろから口腔内環境を整えておくことが非常に大切になります。
まだまだ先が見えず不安やストレスを多く抱えてしまう毎日だと思いますが、苦しみの先にはきっと楽しい日々が訪れることを信じ、その日がきたらより一層いろいろな事にチャレンジできるようお互い健康に気をつけ、また医院でお会いできる事を楽しみにしております。
- 予防歯科について
寒い冬がやっと終わりの兆しを告げ、温かい日差しが強まってきましたね。
桜の開花もすぐそこまで来ているようです。今年は新型肺炎のコロナウィルスの影響で春の卒業式や入学式も縮小され、とまどっている方も多いと思います。
学生の頃の大事な区切りである式典がこのような形になり、とても残念な事とは思いますが、これから健やかな未来を迎えられるように、今はじっと我慢して一人でも多く感染予防につながるよう、努めたいと思います。今日は、健康な歯の為の予防歯科についてお話させて頂きます。
皆さんは、日ごろ歯科医院に予約を入れる時は、どんな時でしょうか?
虫歯によって歯が痛む時?かぶせた義歯が取れた時?歯石の除去やクリーニング?
実は、歯科への通院は中学生以降から徐々に下り坂になり、20代、30代になると歯科への来院頻度は、極端に低くなるということがわかったそうです。学生が終わり、働き出すとますます忙しくなり定期的に歯科へ通う方もとても少なくなるようです。今までの、虫歯発見方法は、肉眼やレントゲンを撮るのが常でしたが、近ごろは、虫歯診断装置(ダイアグノデント)でレーザー光の反射によって虫歯の進行度数が数字で分かるようになりました。このダイアグノデントを使うとレントゲンや肉眼では、発見できない初期の虫歯を見つけられるようになり、数値により以前より詳しく把握できるようになりました。
虫歯になるには、大きく分けて2つに分けられ噛合せなどによる「力の問題」と「細菌感染による問題」です。最近の若い方は「力の問題」が多く、食生活や呼吸器系疾患、免疫力の低下などが考えられます。
噛合せが悪いままにしておくと歯だけでは、なく体の不調にもつながりますので、最新の機器を使い正しいカウンセリングを受け健康な歯の維持に努めて下さい。
レイ歯科でも、ダイアグノデントを使った最新の虫歯治療を行っておりますのでよろしくお願いいたします。
- 細菌の素をなくそう
こんにちは。早いもので気が付けば2月も半ばになり、受験シーズンも峠を越した時期になりましたね。終わってほっとしている方、まだこれからでラストスパートに励んでいる方。それぞれいらっしゃる事と思いますが、大事な決戦の日に虫歯がいたくなったりしないよう早めに歯のお手入れを済ませて頂きたいと願っております。
前回は、「虫歯は細菌感染」というお話をしましたが、今回は細菌の素になる磨きにくい場所について書いていきたいと思います。
普段皆さんは、どのような歯ブラシで歯を磨いていますか?
多くの方は、3列又は4列に配置された歯ブラシで磨いているにでは、ないでしょうか?
しかし、その直線的な歯ブラシだけでは、どうしても磨き残しになってしまいうまく汚れが取れない場所があります。
それは、歯と歯の隙間部分と乳歯の生えたての奥歯になります。
乳児の萌出し始めた歯は、およそ3年間エナメルの質が粗造でありやわらかく、虫歯になりやすい歯になっています。
そのような場所を磨くのに適しているのは、ワンタフトブラシと言ってブラシの部分が円形になり尖っている歯ブラシになります。
直線的な歯ブラシでは、乳児の凹んでいる奥歯はなかなか汚れが取れず虫歯になりやすいのです。
段々と奥歯が盛り上がり、隣の歯に接触するようになるとデンタルフロスなどを使い歯石をため込まないようにしたいものです。大人の方も、ワンタフトブラシやデンタルフロスを上手に使い日ごろから磨き残しをなくし、お口のなかを清潔に保つよう努力して下さい。
寝る前のデンタルリンスなども就寝中の細菌の増殖を抑える効果がありますので、併せてお使い下さい。
その上で、歯科での定期健診、定期クリーニングも忘れずに受けて頂きたいと思います。
- 口内炎のお話
こんにちは。暑かった夏も終わり、やっと過ごしやすい季節になってきました。
実りの秋、スポーツの秋、読書の秋・・・。皆さんは、どんな秋をお過ごしでしょうか?
急に気温が下がり乾燥してきます。体調を崩しやすくなる頃でもありますので、くれぐれもお身体ご自愛下さいね。今日は、お子様の口内炎についてお話させて頂きます。
子供の口内炎は、大きく2つに分けることが出来、1つは、単純ヘルペスウィルスの感染による「ヘルペス性歯肉口内炎」
もう1つは、ストレスや環境の変化などのより起こる「アフタ性口内炎」です。「ヘルペス性歯肉口内炎」は、多くのお子さんには急性症状はみられません。特に歯肉の腫れや出血、舌や歯肉に小さな水疱が生じその水疱が破れると、粘膜は潰瘍のような状態になり、舌は苔で覆われて口臭がみられるようになります。
その為多くの保護者の方は、お口の中の清掃不良と捉えてしまいがちですが、注意したいのは、発熱、倦怠感、食欲不振はお口の清掃不良だけでは、起こらないということです。
より症状を悪化させてしまう事もあるので、そのような症状が出た時の歯磨きは慎重にするようにして下さい。急性期には、水分補給と安静をこころがけ、適度に口腔内を清潔にたもちましょう。一方、「アフタ性口内炎」は、頬粘膜、歯肉、舌に見られる円形あるいは、楕円形の境界明瞭な潰瘍(周りが赤くて中心が白色偽膜の状態)で副腎皮質ステロイド軟膏の塗布や
うがい薬が用いられます。
「ヘルペス性歯肉口内炎」では、副腎皮質ステロイドの投与は、控えなければいけないので注意が必要です。
いずれも、お子さんの食生活に支障をきたすような口内炎は、放置せず早めの来院をお勧めいたします。