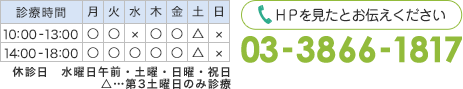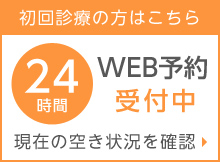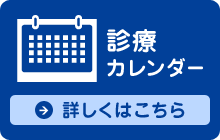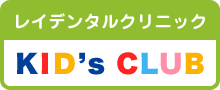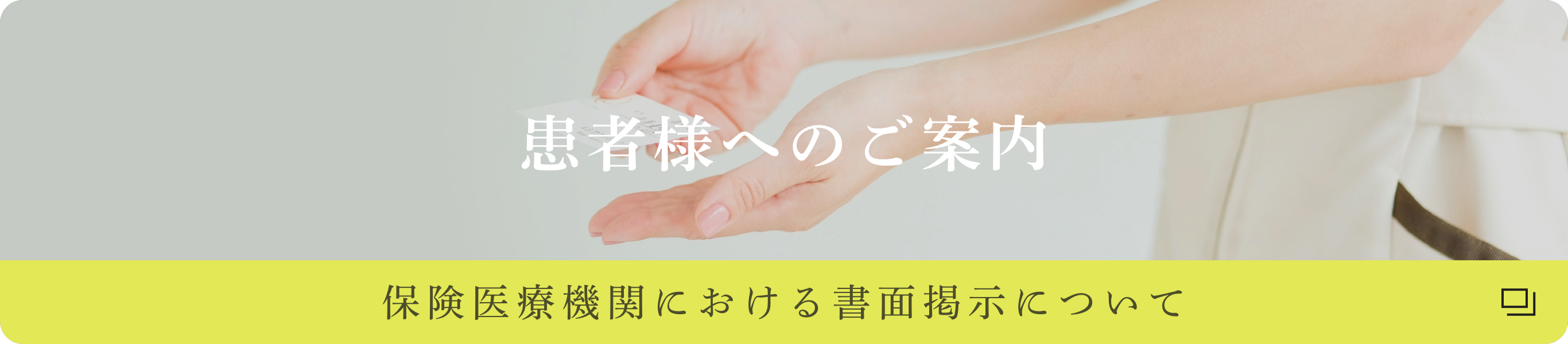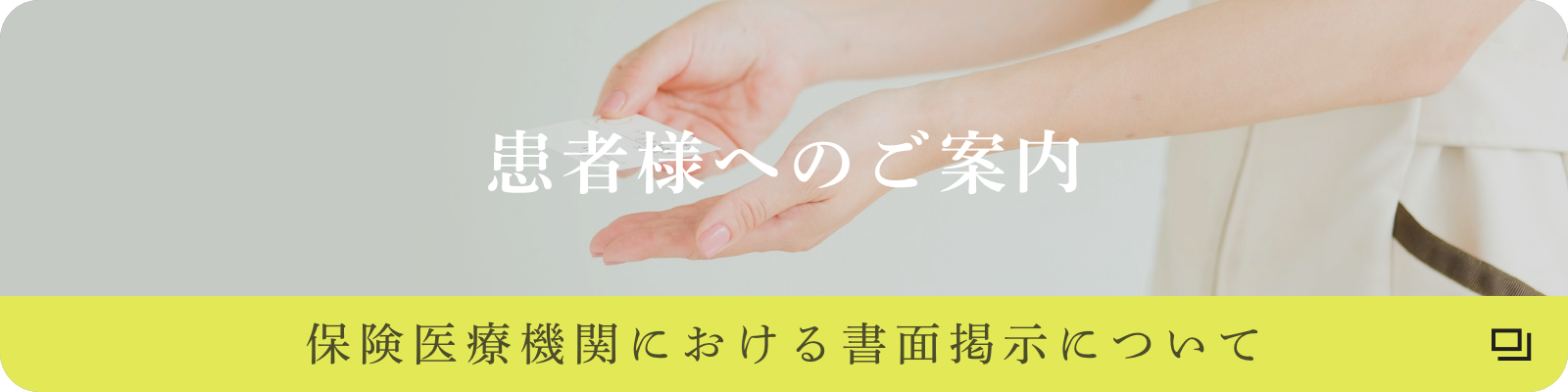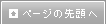あすなの日常
-
2018年12月 5日 水曜日
歯ブラシの選び方
こんにちは。早いもので今年も1か月を切、クリスマスの装飾がされる中お正月商品が並び、気分的にも忙しく感じてしまいます。
寒くなったり急に暖かくなったり気温の変化にご注意ください。今日は、歯ブラシの種類と選び方についてお話したいと思います。
歯ブラシによるプラークコントロールについて
① 生活の習慣として人と接するうえで必要なマナーです
② 疾患の予防として(う蝕や歯周病などの予防)
③ 疾患の治療として
④ 治療後のメンテナンスとして
乳幼児期
歯ブラシを、人生において初めて使うようになるのが、乳児期のお母さんによる仕上げ磨きです。この時期の歯ブラシは、年齢に合わせお母様がしっかりと握りやすく太めの
ものが良いでしょう。ブラシ面は、長方形で植毛は、硬すぎないソフトなものを選びます。
学童期
・学童期用歯ブラシ
学童期は、乳歯と永久歯の交換期となり重要な時期です。
奥歯に虫歯ができないようにネックが長く噛合面に安定してあたる歯ブラシを選びます。ブラシの硬さは、「やわらかい」から様子を見ながら「ふつう」へ変えましょう。
・高学年用歯ブラシ
高学年は、歯磨きが自立する時期です。
第二大臼歯に届くよう、低学年より長いネックで握りやすいものを選び
ブラシの硬さは、「ふつう」をお勧めします。
・思春期~成人用歯ブラシ
中学生でも、口腔の大きさにより高学年用歯ブラシを使い、成長に応じて成人用ラシに変えると良いでしょう。
この時期の歯ブラシは、ヘッドの大きさや植毛の感覚や硬さなど多種多様です。
ヘッドの幅が広い歯ブラシは、全体的に効率よく磨けますが、細部のプラークや歯根部など磨き残しが起きやすいので注意して磨く必要があります。高齢期
・高齢者用歯ブラシ
高齢者の口腔粘膜は、弱く傷つきやすくなっているので、やわらかめの歯ブラシを選び握りやすい太めのグリップの歯ブラシを選びましょう。 -
2018年11月 17日 土曜日
発音のお話
こんにちは!あっという間に気づけば12月になってしまいました。こないだハロウィンで盛り上がりを見せていたかと思ったら次はクリスマスへ町の景色が変わり始めました。
クリスマスが過ぎると、大晦日からお正月とまだまだイベントが続きます。皆様、忙しくて体調を崩さないようお身体ご自愛下さいね。今日は、発音と口腔機能についてお話したいと思います。
発音は、口腔機能と深く関わりがあります。
私たちは、生まれた時から50音すべてが発音できた訳ではありません。日本語に必要な発音が出来るようになるのは、おおよそ6歳~7歳頃だと言われています。
発音の獲得時期や順序などは、個人差があり、就学する頃になっても完全に発音できない子もいます。
上手に発音できない場合は、発音障害の恐れもあり注意深く観察する必要があるでしょう。
発音障害は、大きく分けて3つになり口腔関係によるものは、品質性構音障害と言われ・口唇口蓋裂・不正咬合・舌小帯短縮症などが含まれます。
現在、子供の発音障害では、原因が明らかでない機能性構音障害です。
口腔関係に関わる発音障害の場合歯科での訓練により良くなることもありますので、お子さんの発音が気になる方は一度歯科でご相談される事をお勧めします。 -
2018年10月 17日 水曜日
「歯科医師臨床研修指導歯科医講習会」
こんにちは。東京では、やっと秋らしくなり羽織ものの出番が増えてきましたが北海道からは、早くも雪の知らせが入り、しみじみ日本の国土の長さを痛感させられました。
北海道の方々は、長い冬が始まるのですね。お話は、変わりますが先日、日本歯科医師会主催の厚生労働省「歯科医師臨床研修指導歯科医講習会」に出席させて頂きました。
週末の2日間の目一杯使い日本全国から集まった歯科医の方々と一緒に講師の方々から講習やワークショップやテーマに沿ったディスカッションなどを通して
歯科医師の研修医を受け入れる為のお勉強をしてきました。
1日目の最後に行われた情報交換会では、各地の先生方のお話を聞く事が出来、大変有意義な時間を過ごさせて頂き感謝につきません。
普段の患者様の診療、診断の工程をいかに分かりやすく人に教えるかと言う難しさを痛感して大変勉強になりました。
また、最近の学生や研修医達はこのようなワークショップや勉強法を取り入れているのかと改めて刺激になりました。
研修の修了証の重みをしっかり受け止めてまいります。
これを機に、自分も含めレイ歯科がより一層技術の向上を目指し、地域の方々に還元し喜んで頂けるよう精進したい所存です。 -
2018年10月 3日 水曜日
プレママと赤ちゃんの歯と口の健康について
10月に入り、運動会や遠足など学校行事が増え、それぞれせわしい季節の始まりです。
実りの秋、ハロウィンまで町はかぼちゃ色が増えてきますね。今月より「プレママと赤ちゃんの歯と口の健康」についてお話したいと思います。
妊娠に伴う母体の変化と口腔内への影響
1. ホルモンバランスの変動
妊娠すると、女性ホルモンの分泌量が増えると口周病原細菌が増殖しやすくなり妊娠前よりも歯周病を発症しやすくなります。2. 免疫反応の低下
妊娠すると、血管の透過性が高くなり歯肉が炎症や出血を起こしやすくなります。
また、胎児を異物と見なさないよう母体の免疫が一時的に低下することにより細菌に対する抵抗力が弱くなり、歯肉炎から歯周炎への悪化を招きやすくなります。
3. 唾液の質の変化
妊娠すると唾液の粘り気が高まり、口腔内の自浄性が低下しプラーク(歯垢)の増加につながります。
その為に、「今までと同じにはみがきしても、歯茎から血がでる。」「口の中がねばつく」「歯垢がたまりやすくなった」などといった訴えをよくお聞きします。つわりがもたらす生活習慣の変化と口腔内の影響
つわりは、妊娠初期に特に見られ、感じ方には個人差がありますが食事や歯磨きなどの生活習慣に影響することもあります。
1. 食生活の変化
つわりの時期には味覚、臭覚が敏感になり①食べられるもの限られる②吐き気を感じて食欲不振になる③何かしら食べていないと吐き気を感じる(食べづわり)など、食事の嗜好や食べ方に変化が見られるほか、妊娠後期になると大きく成長した胎児に胃を圧迫され少量づつ数回に分けて食事をとることが増えてきます。2. 口腔ケア不足
妊娠中は、歯ブラシを口の奥まで入れると吐き気を感じ、奥歯の歯磨きが不十分になることがあります。
また、食事回数に歯磨きが追い付かず口腔環境が不良になりがちです。
その結果、う蝕発生や妊娠性歯肉炎を発症したりすることがあります。
安定期に入り、体調が落ち着きましたら地域の「妊婦歯科検診」を受診し予防に努めて頂きたいと思います。 -
2018年9月 15日 土曜日
意外と怖い食いしばり(クレンチング)
暑い夏も終わり、やっと暑さから解放されほっと一息できる季節になってきました。
季節の変わり目、疲れが出やすい時期ですので健康管理には、お気を付け下さい。今日は、食いしばり(クレンチング)のお話をさせて頂きます。
クレンチングとは、本人は、「食いしばっている」自覚なくいつも歯と歯を噛みあわせている人の動作を「クレンチング」と言います。
上下の奥歯と奥歯が深く噛みこんでいる場合、歯列が窮屈な関係ではまり込んでいる方に起こりやすい癖です。
睡眠時に長時間クレンチングをされている方は、アゴの筋肉の疲れや頭部、頸部の筋肉の疲れから頭痛や首、肩の痛みが生じます。
クレンチングは、上下の歯の噛みあわせとも深い関係を持っており、歯と歯を噛みあわせるたびにあそびがない事が、クレンチングを誘発すると考えられています。
ご自分で、このような癖があると思い当たる方は、常に気をつけ、治らない場合は歯科医などと相談し、早めに対策をしたほうが良いでしょう。 -
2018年8月 16日 木曜日
頭とアゴの関係
こんにちは!8月も半ばになり連日の猛暑に少しバテぎみですが、皆さんは体調などくずされていないでしょうか?
暑いと食欲も低下し、体力も落ちてきてしまうので、さっぱりとしつつ栄養もしっかりとれるメニューを考えたいところです。
今日は、顎の位置と体幹についてお話させて頂きます。
頭は、多数の筋によりバランスを保っています。顎は、舌骨と言う骨を介して胸の骨とつながっています。
そして頭とアゴは、左右一対の関節と咀嚼筋によってつながっています。
この為、噛み合わせやアゴの位置は頭とアゴの関係だけでなく、全身の姿勢に強く影響されます。
体に対し、頭の位置に無理があると筋肉の緊張により頭痛や肩こりの原因になります。
人は、脳の容積の増大と引き換えに、物を食べるためのアゴや筋肉を退化させてきました。
その為、貧弱なアゴと頭蓋部の筋肉で、数倍になった脳を支えている為人間は頭痛や肩こりが起きやすい生き物になってしまったのです。
体のバランスと噛みあわせの関係は、このように密接に関係しています。
新保 -
2018年7月 26日 木曜日
顔のバランス
連日の猛暑もひと段落したと思ったら今度は、台風が接近し今週末の隅田川の花火がとても心配です。皆様もお身体ご自愛くださいね。
今日は、顔のバランスについてお話させて頂きます。
顔が左右非対称に見えるのは、筋肉の非対称と骨の非対称、そしてあごや噛み合わせの偏りの為です。
それらの理由は、さまざまですが、顔の外から加えられた力、左右どちらかに偏った顎の使い方、不正な噛み合わせ、姿勢の影響など
いくつもの要因が互いに原因となり、影響し合い顔の非対称が生じます。
うつぶせ寝や、ほおづえ、口の癖など気づかず歪みの要因を自分で作っていることも多々あります。
表情筋は、うすい筋肉になり首の前に広がっている為、激しい緊張や興奮は、首にも表れます。
表情筋の内側には、顎を動かす大きな筋肉があります。
この筋肉は、体を持ち上げるほどの非常に大きな力を発揮しますが、使いすぎるとボディビルダーのように太くなりすぎ、アンバランスが生じます。
また、頭蓋を支え、首を回転させる筋肉のバランス次第で首は、傾きます。
このように、顔のバランスは、お口のまわりだけじゃなく、首や姿勢なども噛み合わせには非常に大きく影響をおよぼします。
次回にまた、その辺のお話をさせて頂きます。
新保 -
2018年6月 7日 木曜日
フッ素についてⅡ
こんにちは!
いよいよ梅雨に入りましたね。今年の梅雨は雨風や台風が来るかもしれなく雨量が多いと言っていましたが、実際はどうなるのでしょう・・・・?!
ジメジメした毎日ですが心だけでもさわやかな日々を送りたいものです。
前回、フッ素のお話をしましたが今日はその続きを書きたいと思います。
「歯科医院で行うフッ素について」
・フッ素を塗る間隔は?
自宅で行う低濃度塗布のフッ素も虫歯予防になりますが、出来れば歯科医院にて高濃度のフッ素を3か月~6か月に1回通院して行う事をおすすめします。
・フッ素塗布を始める年齢は?
フッ素は、歯を強化する働きもあるため歯が生え始めたばかりの赤ちゃんにも有効です。
乳歯が生えそろう1歳頃から歯科医院に通院しフッ素塗布を受けるのが良いでしょう。
・小さなお子さんの初期の虫歯治療にも使います
まだ、小さく一般的な虫歯治療が難しいケースや初期の虫歯には、高濃度のフッ素を塗ることで治療の変わりとすることもあります。
手順としては、口内をクリーニングした後、フッ素を塗布します。これにより、虫歯の進行を止める働きがあります。
「自宅で行うフッ素とは・・・」
・自宅で行えるフッ素塗布は、歯磨き粉、ジェルタイプ、洗口液の3通りあります。
いずれも、「モノフルオロリン酸ナトリウム」「フッ化ナトリウム」と記載のあるものを選びます。
歯磨き粉やジェル状のものは、すすぎは軽くすませましょう。
フッ素洗口液は、お子様の飲み込みなどに気を付けましょう。
ーまとめー
フッ素には、虫歯予防に高い効果があるとされる反面「人体に悪影響があるのでは?」と
不安に思う方もいらっしゃいますが、使い方や適量を守って塗布すれば人体に悪影響を及ぼすことなく
高い虫歯予防を期待できる頼もしい存在です。何か、不安な点がありましたら遠慮なく専門医にお尋ね下さい。
新保 -
2018年5月 30日 水曜日
フッ素のお話
町中のあじさいが鮮やかに色づき始め、梅雨の足音がすぐ傍まで聞こえてきていますね!
雨の日は、気分も今一つ上がりませんが雨上がりのあじさいの花の鮮やかさに下がったテンションも一気に上げてもらえる気分になります。
本日は、フッ素についてお話したいと思います。
1 フッ素は、なぜ虫歯予防になるの?
食事をすると、酸によって歯に含まれるカルシウムやリンなどのミネラルが溶け出します。しかし、通常では唾液が働いて溶け出した成分を元の状態に戻してくれます。
この働きを「歯の再石炭化」と呼びます。
その「再石炭化」を助けるのがフッ素です。唾液中にフッ素イオンが存在していると溶け出したカルシウムがより多くのエナメル質に再吸収されて「再石炭化」を促進し、歯の修復を促すので、出来始めの虫歯を治療し、健康な歯を保ってくれるのです。
フッ素は、歯の表面のエナメル質の成分と結びつき「フルオロアパタイト」と言う硬い構造を作りあげます。この働きにより、ミネラルが溶け出しにくく虫歯になりにくい強い歯にしてくれるのです。
フッ素は、虫歯菌の活動を抑制する働きも持っています。フッ素は虫歯菌の出す酸の量を抑えることが出来、酸により歯を溶かされることがなくなり虫歯を予防する事が出来るのです。
2、フッ素のデメリットって?
通常学校などで習うフッ素は元素記号「F」で表され、単体分子は、常温では気体で空気よりやや重くガラスやプラチナまでも溶かしてしまう「猛毒」の要素を持っています。
そんなフッ素ですが、単体で存在することはなく、自然界では土、川、海、植物など地球上のあらゆる所に含まれており、地球上で暮らす生物は皆フッ素を取り込みながら生きています。
現在、歯科で使われている「フッ素」は、猛毒の単体「フッ素」とは異なる複合体としての「フッ化物」です。正しくは「フッ化ナトリウム」です。
「フッ化物」には「フッ素」ほどの毒はなく、「フッ化物」としての使用法、量や濃度の制限があり、そのような事を守り正しく使用すれば、人体に悪い影響を及ぼすことはありませんので過剰に神経質になる必要は、ないでしょう。
本日は、この辺で、また次回フッ素の続きを話させて頂きます。
新保 レイコ -
2018年5月 16日 水曜日
BBDAパーティ
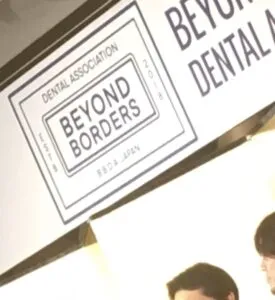
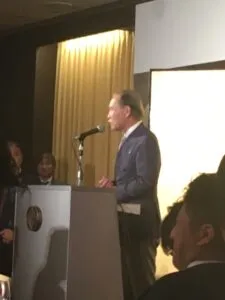
新保です。5月も半ばになり、寒かったり暑かったり天候も不順ですが、皆様いかがお過ごしですか?
先日、2月に参加したボストンハーバード大学の研修会で講義をして下さった先生方が、BBDAキックオフパーティ出席のため来日されまして、パーティ及びセミナーが行われました。
私も、参加させて頂き憧れの先生にも再会でき、他の2月の研修でご一緒した懐かしいメンバーの先生方にも、お会いする事ができて楽しいひと時を過ごす事が出来ました。
次の日に開催されたセミナーにも参加し、ボストンでの講義を思い起こし充実した週末になりました。