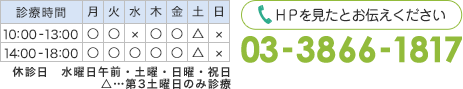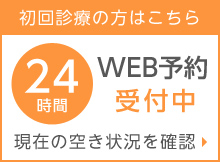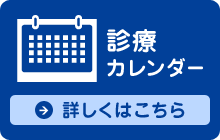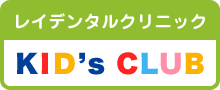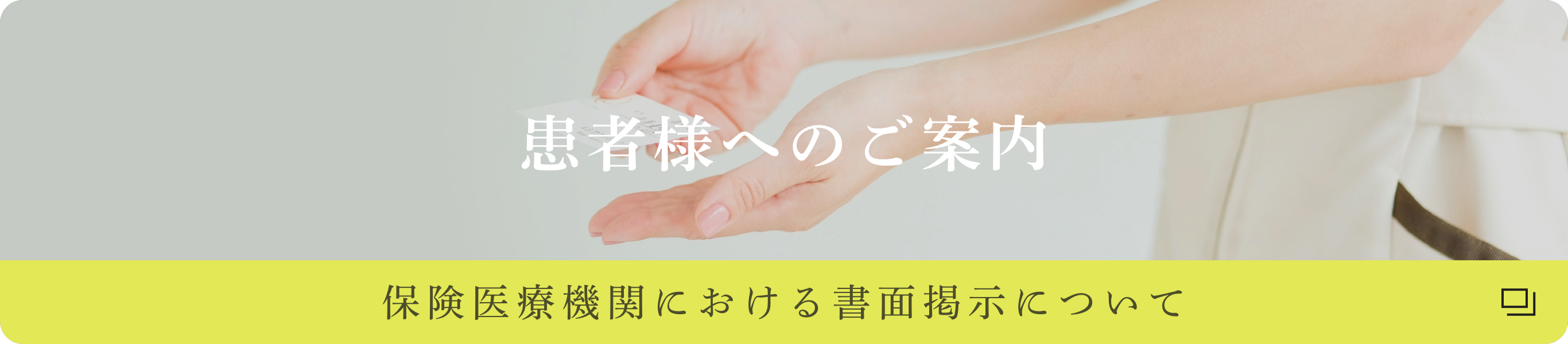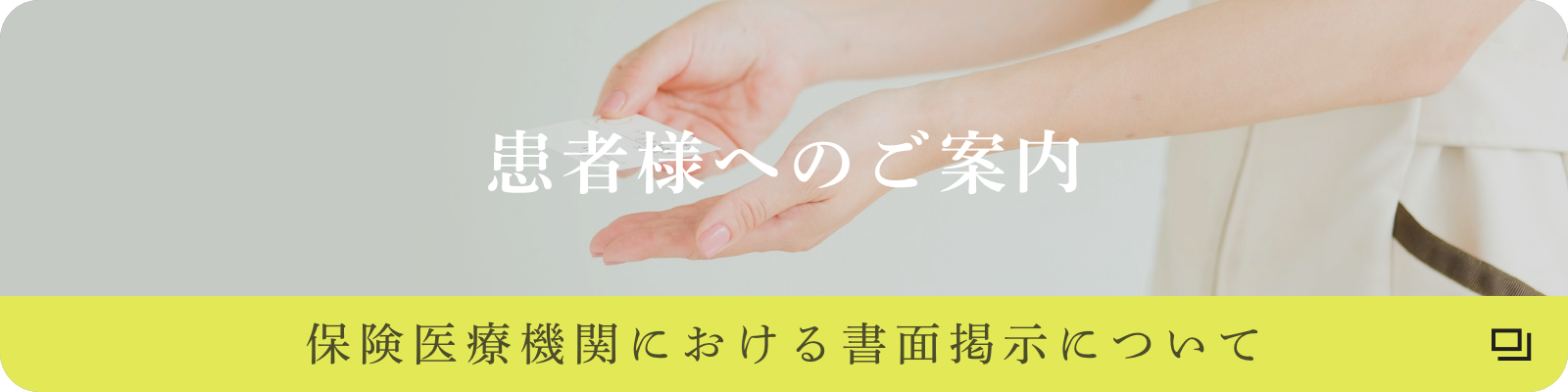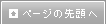あすなの日常
-
2019年11月 13日 水曜日
乳酸菌について
こんにちは!秋も深まり寒い冬はもうすぐ近くまで訪れているようです。
これからの季節、風邪予防に乳酸菌食品を摂り体調管理に役立てている方も多いと思います。
今日は、「なぜ、乳酸菌やビフィズス菌は、体に良いのか・・・・」
と言う事のお話をさせて頂きます。人の体内の腸の中には、約1000種類、100兆個の3つの菌で構成されていてそれぞれ密接な関係を保ちながら健康な腸内を作り上げています。
腸内のバランスは、偏った食生活や不規則な生活、ストレスや加齢、抗生物質の服用などで崩しやすく悪玉菌が増えた場合、病気の発症などに繋がりやすくなってしまいます。健康的な腸内環境は、日々発酵食品や乳酸菌、ビフィズス菌などを摂り腸内の善玉菌が20%前後になるように努めて下さい。ただ、発酵食品や乳酸菌、ビフィズス菌は日々体外に排出されてしまう栄養でもあるので、毎日摂りつづけて頂く必要があります。
それにより、①便通を良くする ②発がんリスクを低減する ③感染症を予防するなどの作用があると言われています。乳酸菌が体に良い!と言うのは分かって頂けたと思いますが、乳酸飲料には乳脂肪や糖分なども多いので、毎日適量の摂取を心がけ継続して続けることにより日々腸内の善玉菌の保持に繋がります。
健康な体は健やかな腸内環境からです。がんばって寒い冬に負けない身体を作りましょう。 -
2019年10月 9日 水曜日
口内炎のお話
こんにちは。暑かった夏も終わり、やっと過ごしやすい季節になってきました。
実りの秋、スポーツの秋、読書の秋・・・。皆さんは、どんな秋をお過ごしでしょうか?
急に気温が下がり乾燥してきます。体調を崩しやすくなる頃でもありますので、くれぐれもお身体ご自愛下さいね。今日は、お子様の口内炎についてお話させて頂きます。
子供の口内炎は、大きく2つに分けることが出来、1つは、単純ヘルペスウィルスの感染による「ヘルペス性歯肉口内炎」
もう1つは、ストレスや環境の変化などのより起こる「アフタ性口内炎」です。「ヘルペス性歯肉口内炎」は、多くのお子さんには急性症状はみられません。特に歯肉の腫れや出血、舌や歯肉に小さな水疱が生じその水疱が破れると、粘膜は潰瘍のような状態になり、舌は苔で覆われて口臭がみられるようになります。
その為多くの保護者の方は、お口の中の清掃不良と捉えてしまいがちですが、注意したいのは、発熱、倦怠感、食欲不振はお口の清掃不良だけでは、起こらないということです。
より症状を悪化させてしまう事もあるので、そのような症状が出た時の歯磨きは慎重にするようにして下さい。急性期には、水分補給と安静をこころがけ、適度に口腔内を清潔にたもちましょう。一方、「アフタ性口内炎」は、頬粘膜、歯肉、舌に見られる円形あるいは、楕円形の境界明瞭な潰瘍(周りが赤くて中心が白色偽膜の状態)で副腎皮質ステロイド軟膏の塗布や
うがい薬が用いられます。
「ヘルペス性歯肉口内炎」では、副腎皮質ステロイドの投与は、控えなければいけないので注意が必要です。
いずれも、お子さんの食生活に支障をきたすような口内炎は、放置せず早めの来院をお勧めいたします。 -
2019年9月 11日 水曜日
「高速ぶくぶくうがい」について
こんにちは。先日の台風はすごい威力で、未だに停電や断水で甚大な被害に合われておられる方がたくさんいらっしゃることに心が傷みます。つくづく、自然の力の強さには、人間の力では、適わないと思い知らされますが、未曽有の災害などの時の被害が大きくならぬよう、普段から今までの災害経験を踏まえ、自治体や国の早急な対応をお願いしたいです。
今日は、「高速ぶくぶくうがい」についてお話いたします。
皆さんは、普段どのようなうがいをしていますか?
「高速ぶくぶくうがい」とは、お口の中の汚れもよく落ち、お口まわりの筋肉も引き締りますのでぜひ、実践してみて下さい。
「高速ぶくぶくうがい」
基本
1、 水30mlを口に含み、1秒間に3回ほど力強く「ぶくぶく」と早くうがいをする。
2、 次は、左右に水が動くように同じように力強く「ぶくぶく」と早くうがいをする。
3、 次は、上下に水が動くように同じように力強く「ぶくぶく」と早くうがいをする。
4、 上記を、10回づつ3セット繰り返す。最初は、口のまわりが疲れますが、毎日繰り返すうちに楽に出来るようになります。
2週間後には、効果が表れ、頬の筋肉がすっきりとし、ほうれい線も薄くなり、口角も上がります。
ポイントは、お水少なめ「ぶくぶく」早めにです。やりすぎには、ご注意を・・・!?気軽に行えるエイジングケア、ぜひお試し下さい。
-
2019年8月 14日 水曜日
Dr.不在のマウスピース?!
お盆休みが始まり、空や道路など日本で一番混む時期に入りましたが、大型台風が
近づいて来てしまい帰省した皆様の交通の乱れなど、とても気になってしまいます。
早く、熱帯高気圧になって消えてほしいと願うばかりです今日は、先日ある書面を見ていて気になった事がありましたので触れさせて頂きます。
そこには、「ネット上で、歯科医師の介入なく作られたマウスピース型製品が販売され、歯列改善への有効性を謳う製品が出てきている。」と言う事でした。
すでに、日本矯正歯科学会は、HPで「歯科医学的にも非常に危険」との注意喚起を出しています。「矯正歯科治療は、正確な診断や精密な治療計画に立脚して行われるべき医療行為であり、誤ったマウスピース型製品の使用は、予期せぬ問題を引き起こす可能性がある。」と指摘しています。
マウスピース型矯正装置による治療は、その利点・欠点を踏まえた適応性の判断や専門知識を要する事から「大学病院等や学会が認めた研修機関にて十分な矯正学を学びトレーニングを受けた歯科医師による治療を推奨する」としています。
私自身、まったくその通りだと共感させて頂き、より多くの方に危険性を唱えていきたい事柄だと思い、お話させて頂きました。
余談ですが、驚いた事に、先日、アメリカのハーバード大学との共同研究で研修に参加した際にお聞きしたのですが、アメリカでは、Dr.不在の店舗にて口の中の状況をデジタルスキャナーで取り込み、それに合わせて3Dプリンターで製作された物を受け取るようです。合理的なアメリカらしい発想ですが正しい歯列矯正学的観点からは、だいぶかけ離れているように思えます。ご自分の大切な歯・・・装置の選択には慎重に・・・。 -
2019年7月 31日 水曜日
虫歯を誘発「スポーツドリンク」とは?
こんにちは。長かった梅雨が終わりやっと夏らしい日が訪れましたね。
気温が上がらず毎日曇りや雨の時には「夏はいつ来るのかね?」などと話し
暑くなり太陽さんさんになると「暑すぎる~!!」などと言い人間は、わがままなものだとつくづく思います。日々自然の恵みに感謝し、たくましく生活したいものですね。今日は、これからの暑い夏にぴったりな話題で「スポーツドリンク」についてお話したいと思います。
こう毎日暑いと、皆さん熱中症対策で水分補給は頻繁に行っている事と思います。
水分補給時にとる飲み物は、どんな飲み物を選んでいますか?
運動時や外出時にお子さんが「スポーツドリンク」を持っていくご家庭も多いと思いますが「スポーツドリンク」は、糖分が多く日常的に飲用していると虫歯をひき起こす要因になりかねません。当院でも、中学生になり、大人の管理下から離れ虫歯になる子が増えています。
実際にお茶と「スポーツドリンク」を用意し、1週間それぞれの中に歯をつけてみた結果、お茶の方は変化せず、「スポーツドリンク」の方は酸により溶かされ脱灰化が進んでいました。
通常歯は、pH5.5以下になると溶けて脱灰が進みます。
体内での吸収力も、蒸留水や糖分なしのお茶などの方が良く「スポーツドリンク」は虫歯になり、吸収もそれほど良くない・・・。では、何を飲めばよいのでしょうか?
それは・・・「経口補水液」です。「経口補水液」の成分の基本は、ぶどう糖2%です。
水分不足時の飲み物は、「経口補水液」をおすすめします。
「経口補水液」は、口から摂取できる「点滴」なのです。
下痢・嘔吐時の速やかな水分補給なども「経口補水液」が適しています。
これからの季節、食中毒や熱中症には、くれぐれもお気を付け下さい。 -
2019年7月 23日 火曜日
「口臭」について
こんにちは。
前回のブログから少し開いてしまいましたが、皆さんお元気でお過ごしでしょうか?
7月は、日照時間が少なく気分も上がらない日々が続きましたが、これから暑くなりますので体調にはくれぐれもお気をつけ下さい。今日は、「口臭」についてお話させて頂きたいと思います。
口腔環境を知るうえで「口臭」問題は重要な役割をはたしています。
体調が悪かったり、寝起きであったり「口臭」について気になる方は、多いのではないでしょうか?
一般的に、「口臭」は、歯周病が原因で起こる事が多いので、歯周病の多い大人の方によく現れる症状です。歯周病になる事が少ない子供の「口臭」が気になるようでしたら
何かの要因が疑われます。
1つ考えられるのは、虫歯です。虫歯が進行するとミュータンス菌が独特の匂いを発します。歯磨きが不十分で食べかすなどが残っていると虫歯になりやすいので注意が必要です。
その他に考えられるのは「口呼吸」です。
寝ている間や何かに夢中になっている時に、お口ポカンで「口呼吸」になっていませんか?通常、子供は唾液の分泌量が多く口の中の自浄作用も強いので「口臭」問題は少ないはずなのですが、お口ポカンで「口呼吸」の習慣がついていると口の中が乾燥してしまい雑菌が繁殖しやすくなり、「口臭」の原因になる事があります。
雑菌が繁殖すると舌に「舌苔」という白い苔のようなものが多く付着するようになりそれも「口臭」の原因になります。
また、ストレスや胃腸の状態なども関係する事があります。
ストレスや胃腸の状態などは、歯科ではなく、すみやかに専門医師のいる病院でご相談する事を、お勧めいたします。
歯科的予防は、常にお口を閉じて鼻呼吸を心がけ、正しい歯磨きをして虫歯のチェックをする。「舌苔」が気になるときには、ゴシゴシとこすらず専用の器具で優しく取り除きましょう。お口が渇かないよう適度な水分補給も忘れずに行って下さい。ストレスは、大人だけでなくお子さんも多く抱えている場合も考えられます。
日ごろから、お子さんとのコミュニケーションをとり精神面のケアも心がけてあげて下さい。 -
2019年4月 23日 火曜日
「お口ポカン」予防トレーニング
こんにちは。あっという間に桜も散り、気温も上がり過ごしやすい季節になりました。
ここら辺では、町会ごとのお祭りの準備も始まり盛り上がってきますね。前回「お口ポカン」について書きましたが、今日は、「お口ポカン」や姿勢の悪さなどを
改善する為のトレーニングについてお話させて頂きます。
「舌の位置」が正しい方は、共通して
・表情が明るい
・血行が良い
・健康的
・鼻呼吸をしていると言う点が上げられます。お口がポカンと開いている癖の事を「口腔習癖こうくうしゅうへき」と言いますが
「口腔習癖」を直し「お口ポカン」を改善する為の基本的なトレーニングをご紹介します。
1、 スポットの位置を覚える
上の前歯の中央部分に歯茎の膨らみがあります。その膨らみ部分がスポットです。
お子さんがわかりにくい場合、親御さんが綿棒などで軽く押してあげたりして教えてあげて下さい。2、 ストローで舌の位置を覚えてお口を閉じる
舌の歯の上にストローを置き、舌をスポットに付けストローを噛んで唇を閉じる
そのまま3分から始めだんだん時間を延ばす。(最大20分)3、 舌を上にキープする「舌の力」をつける
舌の先をスポットに付けそのまま舌全体を上顎に吸いベッタリ付ける。
吸い上げたまま5秒数える。舌をポンッと弾くように下に下ろす。(10回)4、 お口を閉じる筋肉をつける
下唇で、上の唇をグーッと引っ張る(10秒)
上唇の内側に空気を入れる(10秒)5、 唇と表情筋を鍛える
「い」の口をして、口角をギュッと上げる。この時、眉、目、頬、上唇も思い切り引き
上げる。(3秒)
「う」の口をしてお口を思い切りとがらせる。(3秒)
6、 鼻呼吸と正しい姿勢を覚える
壁にかかと、ふくらはぎ、おしり、肩甲骨、後頭部を付け腰に手が入らないようまっすぐ立つ。(3分)
手はおへその舌に添えて、そのままお口を閉じて鼻でしっかりと呼吸する。(3分)7、 鼻で深―い呼吸をする
足の裏全体で立ち、足を肩幅に開きまっすぐ立腕ち、腕を後ろに回し手を組む
姿勢が崩れないよう組んだ手を後ろにひっぱり、そのままお口をしっかり閉じて鼻で腹式呼吸をする。(3分)以上のトレーニングを通じ「お口ポカン」を直し健康的な口元を作りましょう。
ぜひ1度試してみて下さい。 -
2019年4月 11日 木曜日
お口ポカンの影響について
こんにちは!綺麗だった桜もそろそろ終わりを迎え緑の葉っぱが増えてきました。皆様それぞれ今年のお花見は楽しめたでしょうか?
前々回お口ポカンになる原因についてお話しましたが、今日は「なぜ、お口ポカンは、いけない」のでしょうか?
その1つは、口呼吸になってしまうと菌やウィルスが体内に入り込みやすくなり、病気を引き起こす原因になってしまうからです。鼻毛には、ほこりや細菌などを体内に入れないようにフィルターの代わりをしてくれる役割がありますが、鼻の奥には、もっと高
性能な空気清浄化機能を備えた部位がありそこの部位を通り浄化され温められ、十分に加湿されて肺に空気が送られます。
口呼吸になると、十分に加湿されることなくフィルターも通っていないので、有害な菌を体内に入れてしまい喘息や肺炎などが起
こる原因になってしまいます。舌の位置も大切です。本来、人は正しい位置に舌を置くことにより正しい上顎を形成し正しい上の歯が生え、しっかりと噛むことで
下顎も正しく成長します。
舌癖でお口ポカンの方で、舌が低位になってしまうと、あまり表情筋が動かなくなり頬の膨らみが乏しくなり、血色悪く不機嫌そう
な顔に見えてしまいます。
あごの成長で一番大切なのは、舌の位置です。舌が上の前歯裏の中央くらいに常に収まっていることで常に軽い圧力が加わり顎が、
成長します。本日は、ここまでにしたいと思います。次回また少し補足させて頂きますね。
-
2019年2月 20日 水曜日
ハーバード研修CEコース
こんにちは!今日は、気温が一気に上がりだいぶ体にやさしい日となりました。
これから一雨ごとに春が近づき温かくなってきますね。
先日、去年も参加したハーバード大学歯学部の研修会に参加してきました。
最新の歯科治療や歯根の治療の実習など体験し、米国の歯科治療の現状など多数の先生方と意見交換をし、情報を交換出来大変有意義な時間となりました。
普段は、なかなか出来ない体験を研修会に参加させて頂いたおかげで体験出来、とても刺激を受けさらにレイ歯科での治療に役立てたいと思える体験となりました。 -
2019年1月 30日 水曜日
お口ポカンにならない為に
年が明け、ばたばたと過ごしていたら既に1月も終わろうとしています。毎日寒いですが体調など壊していないでしょうか?
新年始めのお話は、「お口ポカン」について書かせて頂きます。「お口ポカン」の始まりは、おっぱいの飲み方や指しゃぶりや、離乳食の食べ方やアレルギーや鼻づまりなどから口呼吸の癖がつくと考えられます。
この一連の動作が正しく行われないと口元にも不具合が生じます。
指しゃぶりは、指を上顎に付けて舌を下に下げる行為です。長期における指しゃぶりは、誤った舌の使い方につながる恐れがありますので、なるべく他の興味をひく話題や遊びに誘ってあげて下さい。
「唇を噛む、吸う、舐める、舌を吸う、噛む」癖は、本来の舌の正しい位置を乱してしまいます。見過ごして長期にわたり続けていると、お口の周りの筋肉の発達を妨げ「お口ポカン」になりやすくなってしまいます。その様な癖を発見したら、やさしく声をかけ、止めるよう導いてあげて下さい。
食事の「丸のみ」や「あまり噛まない」動作も原因になります。
食事を5,6回しか噛まずに飲み込んでしまっているようなら「モグモグ、いっぱい噛もうね!」など、たくさん噛むよう声掛けをしてあげて下さい。最後に、子供は赤ちゃんの頃からお母さん、お父さんの動作をしっかり観察しお手本にしています。ご両親がお口を「ポカーン」と開けてテレビを見ていたり、食事の際に「クチャクチャ」音を立てて食べていたりすると、「テレビを見るときは、お口を開けるんだ!」「食べ物を食べる時は、クチャクチャ音を立てて食べるんだ!」とお手本にされてしまいます。
いろいろと気を付ける所が多いですが、ご自分の動作にも気をつけつつ、お子さんが健やかに成長を出来るよう導いてあげて下さい。何か、気になる癖があり、なかなか治らない時は、遠慮なくご相 談下さい。一緒に対策お考えします。